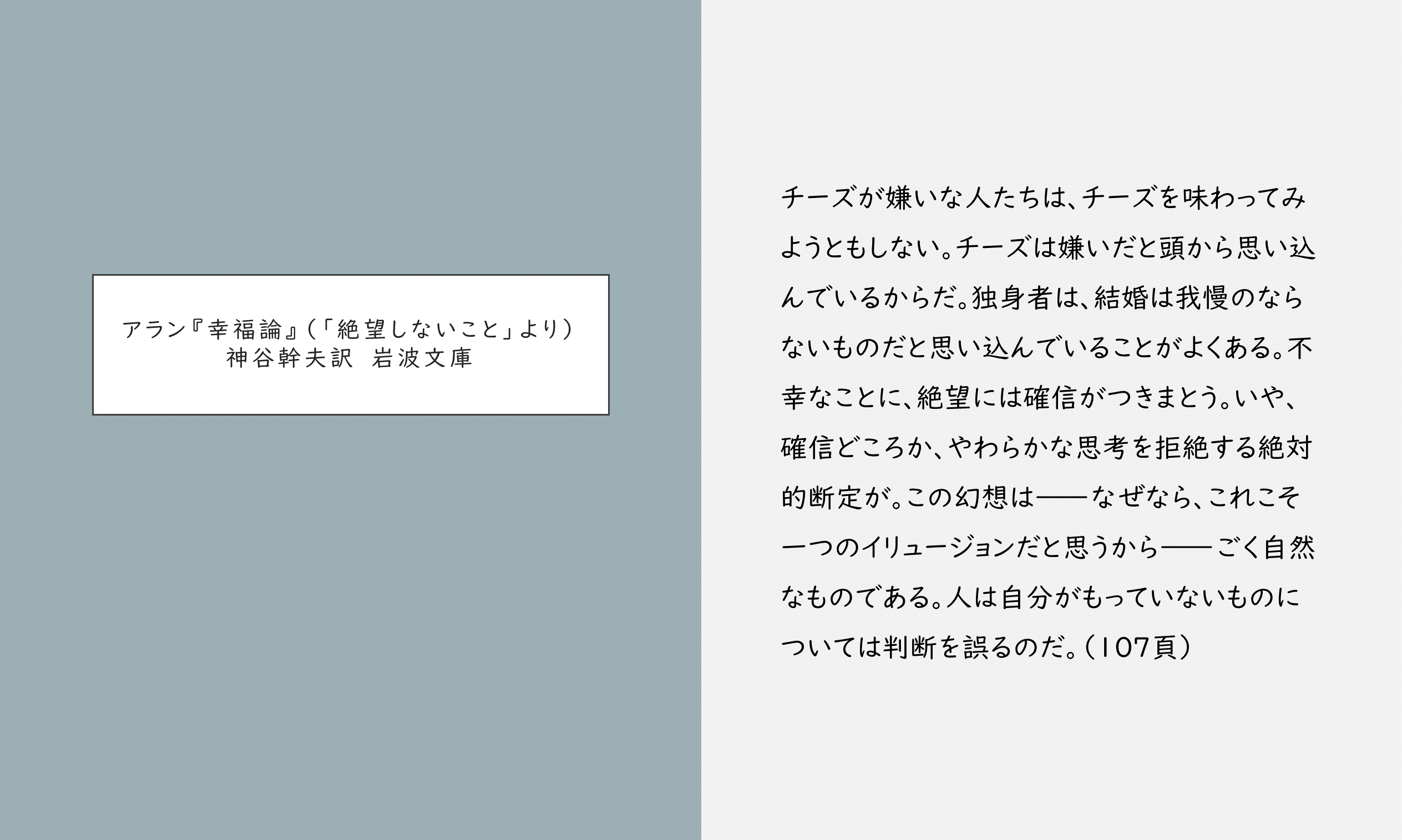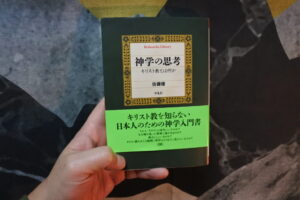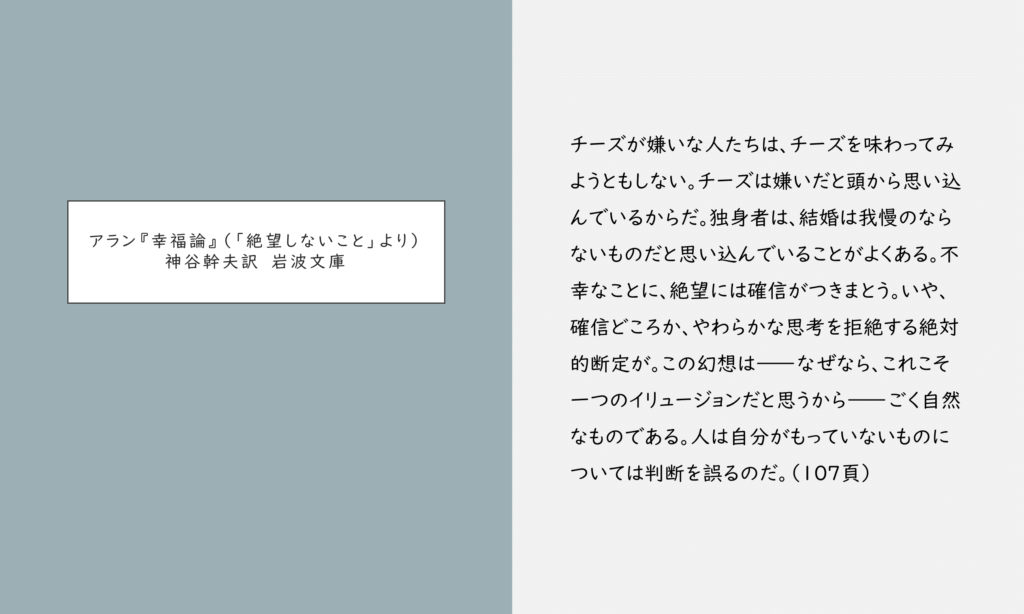
アラン『幸福論』岩波文庫、「絶望しないこと」より。
人は、往々にして、自分が経験したことのないことがらについて否定的に考えてしまう傾向があります。経験したことがないわけですから、当然、自分以外の人たちの意見、一般的な考えを参照せざるをえないわけですが、肯定的な意見よりも否定的な意見のほうが広がり易く、目に付きやすいということも一因であるかもしれません。
曰く、「チーズは臭いものだ」「結婚は(さまざま仕方で)自由を奪うものだ」といった世間の声は、「チーズはとても美味しい」「結婚ほど素晴らしいものはない」のような声を押し退け、多くの人々の目や耳を惹きつけるのではないでしょうか。さらに考えてみれば、チーズが美味しいと思う人のなかには、チーズが臭いものであるがゆえに美味しさを感じる人もいるでしょうし、結婚が自由を奪うものであるとしても、それ以上の素晴らしさを感じることができるのだと考える人がいることは想像に難くありません。ならば、「チーズは臭い」「結婚は不自由だ」という声は、否定側にはもちろん肯定側にも一定数含まれているわけで、結果的に、多くの人が目にすることになると言えるでしょう。そして人は、これらの声を参照して、自分が経験したことがないものを、同じように否定的に捉えてしまうわけです。
アランは、絶望もまた同様だと述べています。
絶望というものは、気がつくと四方を塞がれてしまい、そこからいかにしても逃れるすべがない、身動きが取れなってしまっている精神状態です。絶望は、「もしかしたら、自分が思っているほど大したものではないのではないか」といった可能性すらも拒絶する、それほどの確信をもって、私たちに迫るものだというわけです。絶望の本質を、この文章は的確に表現していると思います。
しかし、この文章が伝えたいのは、人々が絶望に対してもつそのような確信は誤った判断であり、イリュージョンであるということです。ポイントは、チーズの食わず嫌いがチーズを食べたことがないように、未婚の方がまだ結婚したことがないように、絶望に恐れを抱いている人は、未だ絶望に陥ってはいないということです。チーズ嫌いでも、食べたチーズによっては案外悪くなく、むしろ好きになることだってあるわけです。結婚については言わずもがなです。
ならば、今絶望している人は、絶望についての世間の評判を真に受けているにすぎない。そう考えると、もし絶望に陥った場合であっても、「そう大したことはなかったな」「この程度だったか」となる可能性もあるわけです。アランによるこの文章は、絶望のなかにもある種の救いがあることを示唆していると言えるのではないでしょうか。