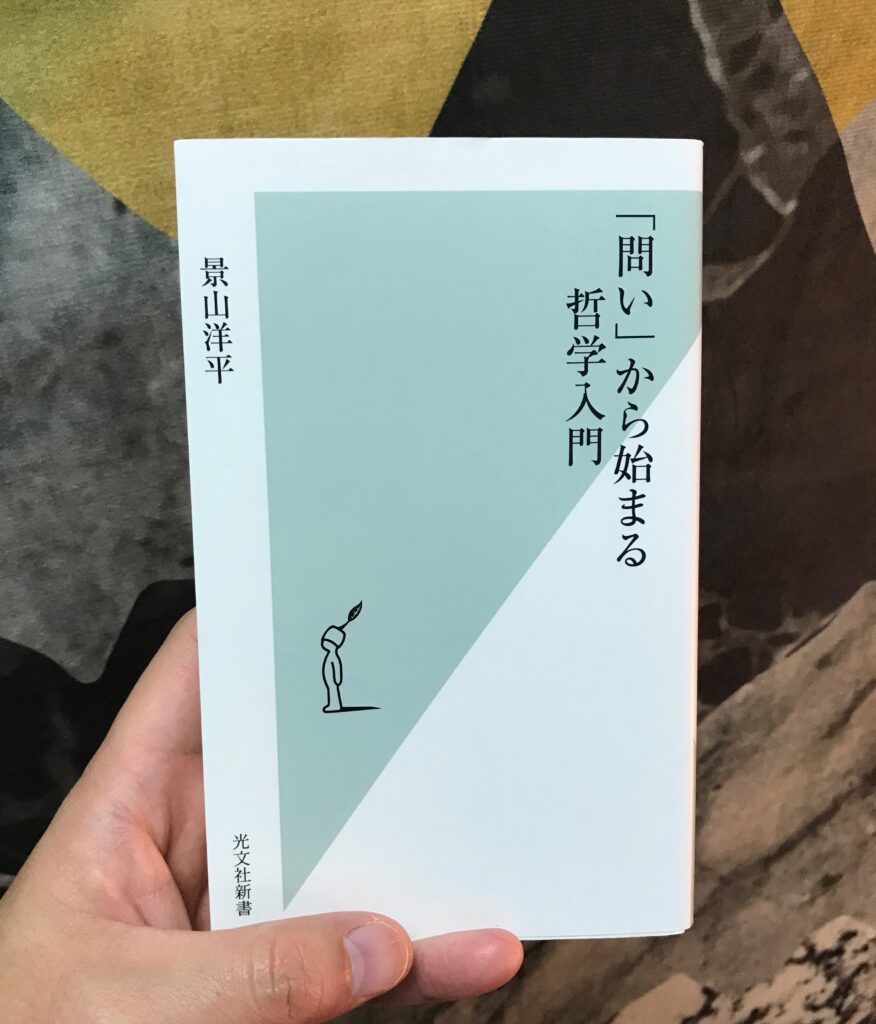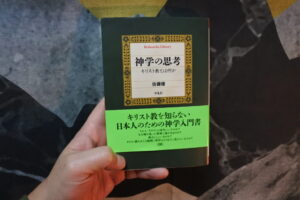入門レベル:★★★☆☆
汎用性(使いやすさ):★★★★★
知的興奮度:★★★★★
世間一般では、哲学というものは答えのない問題ばかり議論している(なので、社会的に無価値だ)とよく言われます。まったくその通りです。なぜなら、哲学にとって重要なのは、答えを出すことよりも問いを立てることだからです。さらにいえば、哲学者たちは、一般的に答えがないとされる問いを提起するとともに、しっかりとその問いにそれぞれの「答え」を与えています。そうすると、「哲学は答えのない問題ばかり議論している」という人たちが求めているのは、哲学者のみならずすべての人類が一致して「これが答えだ!」と認める答えなのでしょうか。そのような答えなるものがこの世に存在しないことは明らかですし、仮に存在するとしても、その答えが出た時点でもはや問いのプロセスは打ち止めになります。もはや何も問いようがない答えを出したところで、それに何か意味があるのでしょうか(とすらも問えなくなるわけです)。
本書の著者である景山氏が言うように、あらゆる疑問を消し去る完全な解答などは存在せず、「「答え」は「問い」を新しく生み出すだけです」(4頁)。そして、哲学というものは、答えがない問いを立て、答えがない問いに取り組み、自ら答えを出し、さらに問いを続ける、このプロセス全体であるということができるかもしれません。
本書『「問い」から始まる哲学入門』(光文社新書)は、まさに、答えがないがゆえにさまざまな哲学者たちがさまざまな観点から「答え」を提示してきた問いに着目し、そこから哲学という人間の根源的な営みを描き出そうと試みます。本書は、「問う」ことを本質とする人間の存在からはじまり、「ある」という問い、実在への問い、「私」とは誰かという問いを経て、まさに、生まれて死ぬべき人間という存在に回帰するように構成されています。このような問いのプロセスは、まさに、古代哲学における「万物のアルケー(始原)とは何か」という問いにはじまり、人間が発見される近代を経て、この世界に否応なく実存させられている人間の本質を問う現代の哲学へと至る、西洋哲学の流れに沿っており、哲学史全体を概観するうえでも優れた本であるといえます。
本書の特徴として、各章はじめのページに、その章で登場する哲学者たちの相関図が用意されています。この相関図を眺めるだけでも面白いですし、哲学者同士の概念的なつながりや影響関係、批判的関係を俯瞰して理解することができます。また、とても多くの哲学者が紹介されているのですが、全体を通して、著者である景山氏が専門とするハイデガーの哲学にしっかりと根差した存在論が通奏低音としてあるため、散漫な記述にならず、哲学の議論の深い部分にまで迷うことなく読者は到達することができます。
一点、哲学を学び始めの初学者の方にとっては、あまりなじみのない哲学者の名前や哲学の議論が所々に登場するので、若干、理解するのが難しい部分があるかもしれません。たとえば、ドレイファスの多元的実在論とマルクス・ガブリエルの「意味の場」を、後期ハイデガーの「四方界」の議論に接続し、多層的なネットワークから成る意味の場が、それ自体変容しつつその都度実在を生みだすという議論は、とても魅力的で興味深いものですが、かなり圧縮された議論が続きますので、理解するのが困難かもしれません。
いずれにしても、この実在論に関するあらたな「答え」をはじめとして、本書に読まれる議論がかなりの知的興奮を与えてくれることは間違いありません。