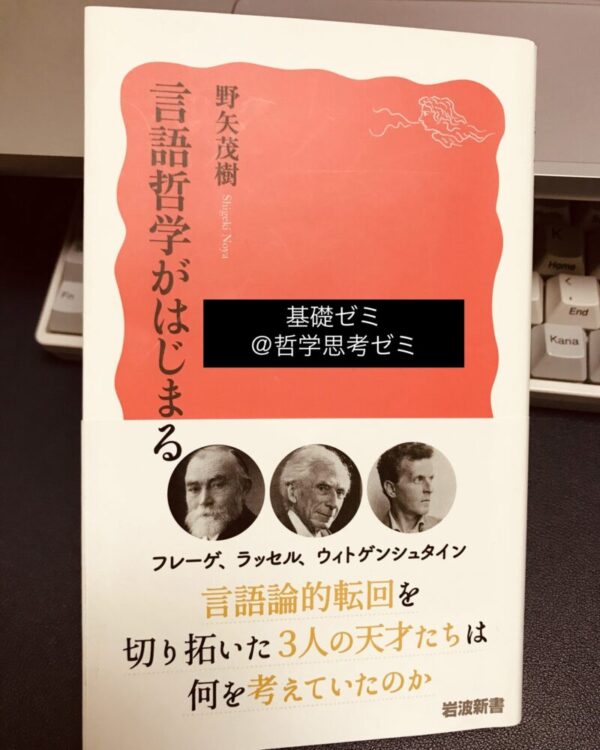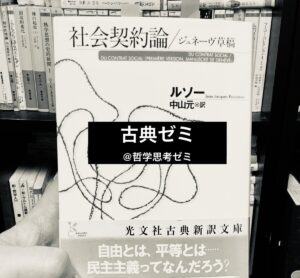みなさま、こんにちは。ソトのガクエンの小林です。
哲学思考ゼミ・基礎ゼミのテキストが2月より野矢茂樹『言語哲学がはじまる』(岩波新書)に変わり、先日初回ゼミが行われました。
基礎ゼミでは、毎回リーダー(reader)が担当箇所をレジュメやスライドにまとめてきたものをもとに、参加者の皆さんと議論する形で進めています。初回は、小林(ソトのガクエン代表)がリーダーとなり第1章「一般観念説という袋小路」を読みました。
今回読んだ内容は、なぜ私たちは、文を無際限に作り出すことができ、それを理解することができるのかという問い(本文では「新たな意味の算出可能性の問題」と名指されています)に対し、文の意味が理解できるのは、それに先立って語の意味を理解しているからだという考え方について検討されていきます。
それでは、語の意味とは何か?例えば、「富士山」という語が現実に存在する一つの山である富士山を意味するように、語は現物を提示する(指示対象説)ということが考えられます。しかし、「富士山」のように一つの対象(個体)の名前である固有名の場合は、このような指示対象説をクリアできるとしても、「猫」のような一般名は、それに対応する個物が存在しません(あの猫でもこの猫でもなくどの猫でもない猫一般)。そこで、猫一般はこの世界に存在しないが、心の中に一般観念として存在するとするジョン・ロックの議論が紹介されます。
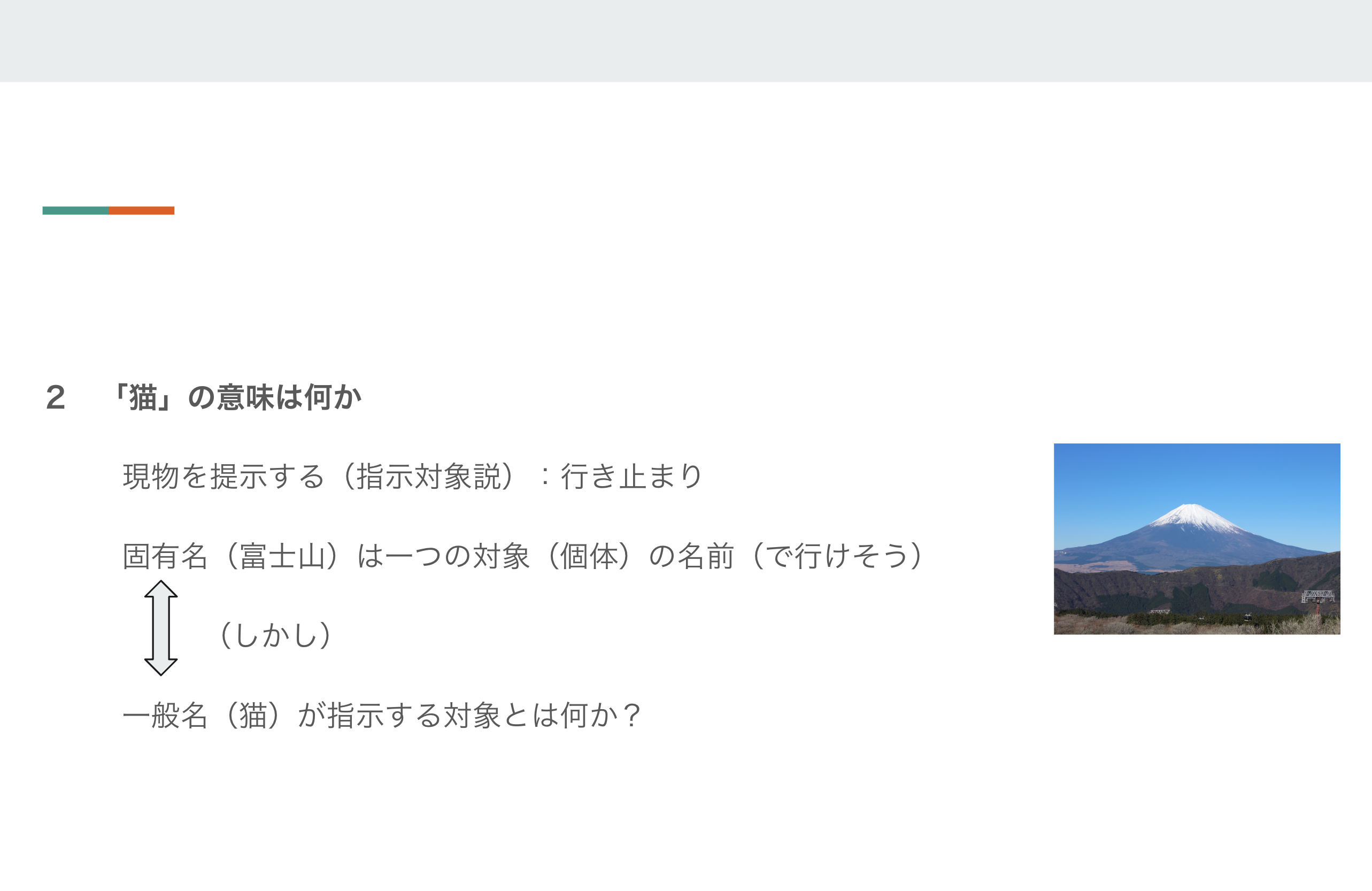
しかし、ロックの一般観念説には批判があり、①心の中に一般観念を思い描くことはできない(バークリー)、②一般観念が心の中に形成されたとしても、他人がどのような意味で一般名を用いているのか分からない(フレーゲによる心理主義的批判)、③心の中も世界の中に過ぎず、心の中で出会う対象も個別的なものでしかない(ウィトゲンシュタイン的批判)が本文では紹介されます。これにより、一般観念説によっては、語の意味を捉えることができないということが確認されます。さらに、そもそも、文の意味に先立ってまず語の意味を捉えようとする方針が誤っているとして、第二章の「文の意味の優位性」へとリレーされることになります。
****
さて、当日の参加者のあいだでは、本文中に出てくる「言葉は、一般観念の記号とされることによって一般的となる」というジョン・ロックの『人間知性論』の部分を巡って様々な議論が起こりました。この文は、一見するとトートロジー(言葉は一般観念を指示するから一般的である)を述べているだけではないかと参加者の方からのご指摘がありましたし、本文でも、説明なく書かれていた箇所だと思います。
おそらく、ここに見られる「記号とされること」という部分が重要で、単に個物に名前をつけるだけでは記号(自らとは別のものを意味するもの)とはならず、どのタイミングで、どのような条件のもとで名前が記号となるのかを考える必要があります(ゼミ内では、ある語に対して、少なくとも二人以上の共通理解が必要では?という話をしていました)。実際、ロックの『人間知性論』でも、すべての個物に名前をつけることは可能ではあるが、他人とのコミュニケーションにおいては無用であり、一般観念を形成する必要があること、あるいは、個別観念と個別観念の共通特性から複合されたものに名前をつけることで個別観念が包摂される一般観念となるというプロセスが重点的に説明されています。いずれにせよ、一般観念の存在如何がテーマとなる本文では省略可能な議論であるため、このような圧縮された表現になったのではないかという話をしていました。
第1章の内容は、さほど難しいものではなく、文章もリーダブルで分かりやすいものでした。しかし、指示とは何か?、記号とは何か?、シグナルとシンボルの違いは?等々、いろいろな観点から言語について考えてみると、議論が必要な様々な論点があることが明らかになりました。次章以降、これらの疑問にどれだけテキストが応えることになるのかを考えながら読み進めたいと思います。
次回の基礎ゼミは、2月13日(土)22時からです。Kさんをリーダーに、第2章「文の意味の優位性」から読んでいきましょう。
哲学思考ゼミでは、基礎ゼミ、古典ゼミ、シネマ読書会、表現スキル思考ゼミ、大学院進学情報&原書ゼミ、自主勉強会にご自由にご参加いただけます。すべてのゼミは限定YouTubeでご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。
ソトのガクエン「哲学思考ゼミ」HP→https://www.dehors-org.com/seminar