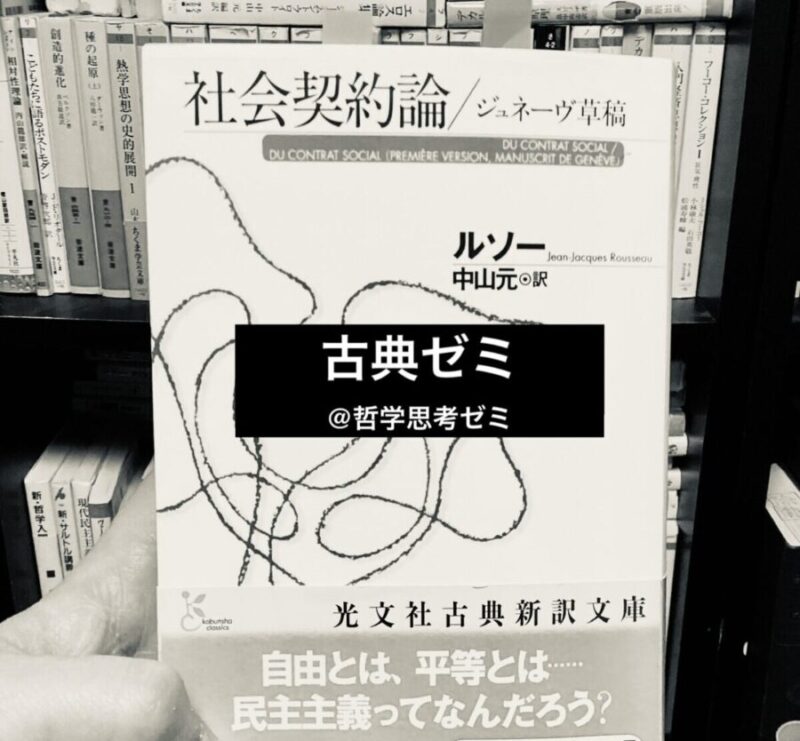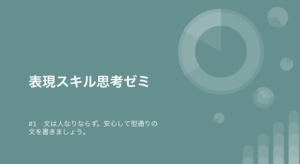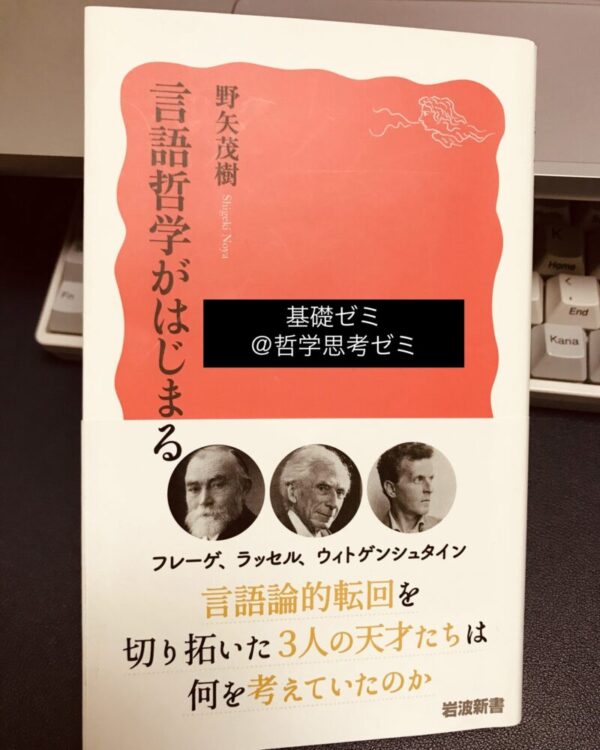みなさま、こんにちは。ソトのガクエンの小林です。
2月3日(土)から古典ゼミのテキストがルソー『社会契約論』(光文社古典新訳文庫)に変わり、先日、初回が行われました。今回は、冒頭から第一編の第三章「最強者の権利について」(26頁)まで読み進めました。
まず、冒頭に登場するのですが、政治について書くなんて、あなたは君主か立法者かと尋ねられたら、私はそのいずれでもない、ないからこそ政治について考察するのであり、もし君主や立法者ならば、何も言わずただ自分がなさねばならぬことをするのみである、というルソーのレトリックとその姿勢にとても痺れました。
****
さて、今回読んだ箇所では、社会秩序というものは自然から生まれたものではなく(このあたり、自然状態に生きる人々が、自然に備わった情念と理性によって自ずと社会を形成するというホッブズの議論が仮想敵になっているように思います)、合意に基づいて生まれたものであるとされます。
ルソーは、最も原初的な社会とは家族であるといいます。父親は、自分ひとりで生きることができない子どもを扶養する義務があり、子どもは自分ひとりで生きることができないので、父親に服従する義務があります。とすると、子どもが自立し、ひとりで生きるようになれば、お互いの扶養と服従の義務は解消されます。その後も、家族の結びつきを望むとするならば、それは合意にもとでしか維持されません。こうした家族をルソーは政治社会の最初のモデルであるとします。「誰もが平等で自由な存在として生まれた」人間は、「自らの利益にならないかぎり、自由を譲り渡すことはない」。では、国家が個人を服従させる、そのような合意が何によって生まれるのか、そして、いかにしてそれを維持しうるのかを考えるのが『社会契約論』のテーマとなります。
参加者の方々で議論になったのは、ルソーやホッブズのいう「自然状態」についてです。自然状態は国家が存在する以前の状態ですから、いかなる資料もいかなる文書も残されておらず、その意味で歴史の外部にある「自然」であり、現世を生きる私たちには決して到達しえない「自然」です。したがって、自然状態も自然状態からの国家の成立も、当然ながらフィクションにならざるをえません。ここである参加者の方は、そもそも「自然」というものが、「これが自然である」という人間の認識があってはじめて可能となるのであり、その外部に自然など存在しないのではないかと言われました。これに対して別の参加者の方からは、しかし、人類が誕生する以前の地球も物理的には存在しているのだから、これは人間の認識以前に存在するといえるのではないかという意見がありました。このあたりは、カント的な相関主義とこれを批判する思弁的実在論の論争の形が再現されているかのようです。
相関主義的立場からすると、地層に埋まった化石などを通して私たちが知るのは人間以前に存在する自然ではありますが、しかし、それもまた人間が、化石を介して「自然である」と知ることのできる、認識の内部に位置する自然に過ぎないとも言えます。これに対して、それはまさに相関主義的立場から化石が示すものを理解しているに過ぎず、相関主義の外部にある存在を思考してはいないと反論されることになる。もちろん、何かの答えがあるわけではないのですが、いろいろな哲学的な議論を展開することのできる、とても興味深い問題だと思います。
※思弁的実在論による相関主義批判については、カンタン・メイヤスー『有限性の後で』(人文書院)を参照ください。
さらに、他の参加者の方からは、哲学者の主張はつねに言語でなされる以上「フィクション」にならざるをえないが、哲学者たち本人は自分の主張がフィクションだとは思っていないのではないかという話がありました。おそらく、プラトンにとってイデア説は、フィクションではなくむしろそれこそが真理であるし(プラトンの場合、われわれの用いる意味でのフィクションに該当するのはドクサとなるかと思います)、カントの道徳原理やヘーゲルの絶対精神などは、未だ存在しないという意味ではフィクションとも言えますが、彼らにとってはむしろ、それを目指して進むべき、実現すべき「理念」であるはずです。
おそらくフィクションというのは、人間(認識)と世界が分離している以上、すなわち、人間が有限である以上、人間と世界そのものとの間に乖離が生じることに起因するものです(ならば、世界と完全に一致する神にとってフィクションはありえません)。したがって、この意味では、哲学的言説はすべてフィクションであることになります。ただ、同じフィクションでも、優れたフィクション、合理的・妥当性のあるフィクションというものは存在しますし、「真に存在する世界」というものがあるとすれば、有限な私たちにとってはどのようにしてもそこに到達できないのですから、その極限にまでいかに漸進的に迫ることができるのか、いかにその極限を思考できるのかということが、哲学がなすべきことではないでしょうか。このような話をしていました。哲学とフィクションというテーマもまた別に考えるべき面白い議論です。
次回の古典ゼミは、2月10日(土)22時からです。第二章「最初の社会」の「支配者の地位」から読んでいきましょう。
哲学思考ゼミでは、基礎ゼミ、古典ゼミ、シネマ読書会、表現スキル思考ゼミ、大学院進学情報&原書ゼミ、自主勉強会にご自由にご参加いただけます。すべてのゼミは限定YouTubeでご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。
ソトのガクエン「哲学思考ゼミ」HP→https://www.dehors-org.com/seminar