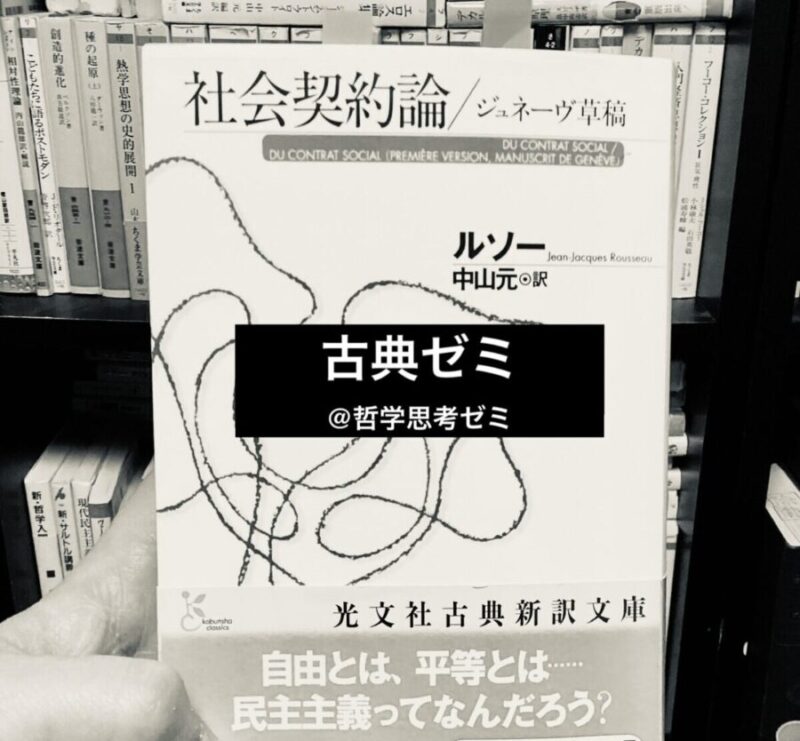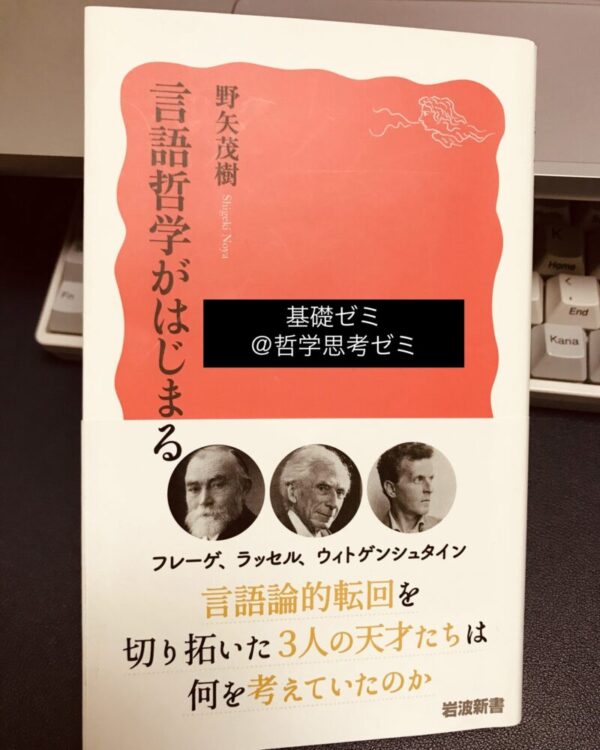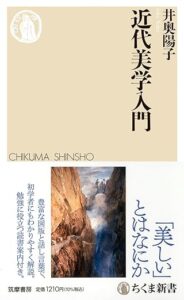みなさま、こんにちは。ソトのガクエンの小林です。
今回の古典ゼミは、『社会契約論』(光文社古典新訳文庫)21ページ「支配者の地位」から読み進めました。主な論旨としては、支配者が被支配者を服従する権力が何によって生じるのか、さらに、被支配者が支配者に服従する義務がいかに生じるのかが考察されます。とはいえ、具体的にその原因が示されるというよりは、権力と服従についての一般的な考え方が批判的に検討される箇所です。
まずは、支配者の権力は、支配される者たちの利益のために確立されたものであるという考え、さらには、牧者が家畜よりも優れているのと同様に、この世界には支配する側の人間と、支配される側の人間がもともと決まっているという考えが批判されます。後者の考えは、アリストテレスやホッブズにもみられるものですが、たとえば、アダムは人類の最初の人間ですが、すべての人間はアダムの末裔なのだから、私にも人類の正当な王の資格があるかもしれないではないかと批判されることになります。
また、権力とは身体的な力であって、不可避的に服従せざるをえないことがあっても、そこから服従する義務や、服従しなければならないといった道徳性は生まれないとルソーは説明します。「力はいかなる権利をも作りだすものではない」。私たちが服従する義務が生じる正当な権力が成立するとすれば、それは合意によるものだけであるとルソーは言います。ではそれはどのような合意であり、それがどのように成立するのかが議論されることになります。
今回の箇所で参加者の方々と議論になったのは下記の部分です。
子供たちが理性を行使できる年齢になるまでは、父親が代わりに子供たちの生存と福祉のための条件を定めることはできる。しかし子供たちを無条件で、撤回することのできない形で他人に与えることはできない。このような贈与は自然の目的に反するものであり、父親の権利の範囲を超えたものだからである。(29頁)
ルソー『社会契約論/ジュネーヴ草稿』、中山元訳、光文社古典新訳文庫、2008年、29ページ。
第二章冒頭で、子が自立できない間は父に扶養の義務が、子には服従の義務が生じるのであり、家族関係とは、自然における最初の社会であると言われていました。引用箇所は、家族関係という自然の目的を終えた後において、そもそも自由な存在として生まれた一人の人間の自由を誰かに譲り渡すことは、父親でもできないと述べているかと思います。ここでの「子供」は、では、父親に服従している間であれば、「子供たちの生存と福祉のため」であれば、他人に譲り渡すことはできるというように読めるのではないかという意見があがりました。有名な話ですが、ルソー自身自分の子供を5人孤児院に捨てていますので、このケースはこれに該当するかもしれません。さらには、ルソーによって「子供」という概念が発見されたという話、フィリップ・アリエス『〈子供〉の誕生』についてなどなど、色々な話題についてお話しすることができました。
次回の古典ゼミは、2月17日(土)22時からです。第四章「奴隷について」の「自由の放棄」から読んでいきましょう。
哲学思考ゼミでは、基礎ゼミ、古典ゼミ、シネマ読書会、表現スキル思考ゼミ、大学院進学情報&原書ゼミ、自主勉強会にご自由にご参加いただけます。すべてのゼミは限定YouTubeでご覧いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。
ソトのガクエン「哲学思考ゼミ」HP→https://www.dehors-org.com/seminar